

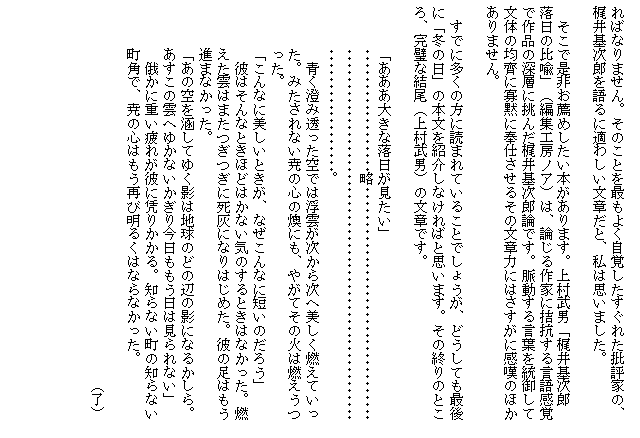
黒子和雄の《戦争レクイエム》第三作「父と暮せば」完成の記事が先日新聞に載りました。井
上ひさしの同名の芝居を忠実に映画化したということですが、その戯曲の方をこの前竹崎君に
借りて読みました。
上ひさしの同名の芝居を忠実に映画化したということですが、その戯曲の方をこの前竹崎君に
借りて読みました。
この作品の舞台が被爆地ヒロシマですから当り前と云えば当り前のことなのですが、「美しい
夏キリシマ」が宮崎弁一色であったように、ここでもせりふ台詞は全編見事な広島弁です。大
阪から、広島とは逆の東へ向う列車の中で読みはじめたのですが、道中私はすっかり広島弁
の世界に嵌り込んでいたので、目的地の小田原の駅についたときは一瞬の途惑いを覚えたほ
どです。日頃巷の涸渇した言葉の廃墟の中で暮らしていると、展けた方言の沃野につい引き
入れられてしまうのかもしれません。
夏キリシマ」が宮崎弁一色であったように、ここでもせりふ台詞は全編見事な広島弁です。大
阪から、広島とは逆の東へ向う列車の中で読みはじめたのですが、道中私はすっかり広島弁
の世界に嵌り込んでいたので、目的地の小田原の駅についたときは一瞬の途惑いを覚えたほ
どです。日頃巷の涸渇した言葉の廃墟の中で暮らしていると、展けた方言の沃野につい引き
入れられてしまうのかもしれません。
映画では、黒木和雄が戰友と呼ぶ父親役の原田芳雄と、娘を演じる宮澤りえの二人がどん
な美しい広島弁を聞かせてくれるか大いに楽しみです。因みに、宮澤りえについては、稀に見
る女優になるのではないかと、「たそがれ清兵衛」以来密かに私はそう思っています。
な美しい広島弁を聞かせてくれるか大いに楽しみです。因みに、宮澤りえについては、稀に見
る女優になるのではないかと、「たそがれ清兵衛」以来密かに私はそう思っています。
「父と暮せば」は、東京で七月中旬から上映されると記事にはありました。しかし例によって
大阪では何時になることやら。『ちょっと東京まで映画を見に行ってくる』こんなゼイタクを一度く
らいやってみたいものですね。
大阪では何時になることやら。『ちょっと東京まで映画を見に行ってくる』こんなゼイタクを一度く
らいやってみたいものですね。
《追記》
ゼイタクできない人に朗報です。七月九日付の夕刊に《「父と暮せば」は大阪のテアトル梅
田、アポロホールで八月公開の予定》と、嬉しいニュースを見つけました。
田、アポロホールで八月公開の予定》と、嬉しいニュースを見つけました。
日曜日の日経新聞の読書欄に『半歩遅れの読書術』という月毎に筆者の替るコラムがありま
す。六月担当の張競(zhan jing ・比較文学者)がその第一週目に「言葉の脈動」と題して梶井
基次郎の作品を取り上げていたのを興味深く読みました。ことに日本語を母語としない研究者
の日本語に対する鋭い感応力と卓越した彼自身の日本語表現力など、惹かれるところが多か
ったので、長さを厭わずほゞ全文に近くを紹介いたします。
す。六月担当の張競(zhan jing ・比較文学者)がその第一週目に「言葉の脈動」と題して梶井
基次郎の作品を取り上げていたのを興味深く読みました。ことに日本語を母語としない研究者
の日本語に対する鋭い感応力と卓越した彼自身の日本語表現力など、惹かれるところが多か
ったので、長さを厭わずほゞ全文に近くを紹介いたします。
(前略)
明治以来の浩瀚な作品群の中でつよく印象に残ったのは、梶井基次郎の『檸檬』である。
よく読む作家なら、夏目漱石をはじめほかにも多くいる。しかし、文体の驚きというか、言葉
が直接心に響いてくるのはやはりこの短編集だ。とくにはじめて「冬の日」を読んだ時の衝
撃は強烈なものであった。自然と心象が互いに隠喩的な関係としてこれほど鮮やかに描か
れた作品は見たことがない。
よく読む作家なら、夏目漱石をはじめほかにも多くいる。しかし、文体の驚きというか、言葉
が直接心に響いてくるのはやはりこの短編集だ。とくにはじめて「冬の日」を読んだ時の衝
撃は強烈なものであった。自然と心象が互いに隠喩的な関係としてこれほど鮮やかに描か
れた作品は見たことがない。
「冬の日」には物語らしい物語はない。が、読んでいて何か軽やかな風が情感の深部に吹
き込んできたようだ。このふしぎな感触は新鮮である。とりわけ、それが思いもよらない言
葉の無限花序として不意に現われた時は。
き込んできたようだ。このふしぎな感触は新鮮である。とりわけ、それが思いもよらない言
葉の無限花序として不意に現われた時は。
(中略)
母語で文学作品を読むとき、言語表現上のオリジナリティーがあるかどうかは直感的に
把握できる。しかし、非母語の場合、意識的な分析をしないと感じ取りにくい。意味の理解
を優先させがちだから、文体やレトリックなどに対する感度が鈍くなりやすいからだ。だが
「冬の日」は非母語の読者にも言葉の脈動がじかに伝わってくる。それまで誰も使ったこと
のない語り方で、どこにでもありそうな日常の断片を、一瞬にして非日常の陰翳に転換させ
る手法には驚嘆するしかない。
把握できる。しかし、非母語の場合、意識的な分析をしないと感じ取りにくい。意味の理解
を優先させがちだから、文体やレトリックなどに対する感度が鈍くなりやすいからだ。だが
「冬の日」は非母語の読者にも言葉の脈動がじかに伝わってくる。それまで誰も使ったこと
のない語り方で、どこにでもありそうな日常の断片を、一瞬にして非日常の陰翳に転換させ
る手法には驚嘆するしかない。
言葉には生命が宿っている。この短編を読み返すたびにそう思う。
美しい作品について語るとき、それは美しい言葉で語らな
ければなりません。そのことを最もよく自覚したすぐれた批評家の、梶井基次郎を語るに適わ
しい文章だと、私は思いました。
しい文章だと、私は思いました。
そこで是非お薦めしたい本があります。上村武男「梶井基次郎 落日の比喩」(編集工房ノ
ア)は、論じる作家に拮抗する言語感覚で作品の深層に挑んだ梶井基次郎諭です。脈動する
言葉を統御して文体の均齊に寡黙に奉仕させるその文章力にはさすがに感嘆のほかありま
せん。
ア)は、論じる作家に拮抗する言語感覚で作品の深層に挑んだ梶井基次郎諭です。脈動する
言葉を統御して文体の均齊に寡黙に奉仕させるその文章力にはさすがに感嘆のほかありま
せん。
すでに多くの方に読まれていることでしょうが、どうしても最後に「冬の日」の本文を紹介しな
ければと思います。その終りのところ、完璧な結尾(上村武男)の文章です。
ければと思います。その終りのところ、完璧な結尾(上村武男)の文章です。
「あああ大きな落日が見たい」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
青く澄み透った空では浮雲が次から次へ美しく燃えていった。みたされない尭の心のお
燠にも、やがてその火は燃えうつった。
燠にも、やがてその火は燃えうつった。
「こんなに美しいときが、なぜこんなに短いのだろう」
彼はそんなときほどはかない気のするときはなかった。燃えた雲はまたつぎつぎに死灰
になりはじめた。彼の足はもう進まなかった。
になりはじめた。彼の足はもう進まなかった。
「あの空をひた涵してゆく影は地球のどの辺の影になるかしら。あすこの雲へゆかない
かぎり今日ももう日は見られない」
かぎり今日ももう日は見られない」
俄かに重い疲れが彼によ凭りかかる。知らない町の知らない町角で、尭の心はもう再び
明るくはならなかった。
明るくはならなかった。
(了)
|
|

