― わが畏友、陶工の生田和孝は、日本陶芸展の文部大臣賞を受賞するなど、そ
の将来を大いに嘱望されながら若くして亡くなりました。あらためて思い起せ
ば、その死から二十年を越える歳月が流れたことになります。
の将来を大いに嘱望されながら若くして亡くなりました。あらためて思い起せ
ば、その死から二十年を越える歳月が流れたことになります。
去る日、兵庫県民芸協会の会長・津田義文先生から、生田さんのことについ
て何か書いてくれないかと依頼を受け、書きしるしたものが、今月発行の『兵
庫民芸』の31号に掲載されました。
て何か書いてくれないかと依頼を受け、書きしるしたものが、今月発行の『兵
庫民芸』の31号に掲載されました。
「獨木舟文学館」 のホームページに載せるには異質なものという感じは否めませ
んが、本文にある通り、獨木舟に所縁のある人物のことでもあり、また竹崎君
のすゝめもあったので、敢えて発表することにしました ―
んが、本文にある通り、獨木舟に所縁のある人物のことでもあり、また竹崎君
のすゝめもあったので、敢えて発表することにしました ―

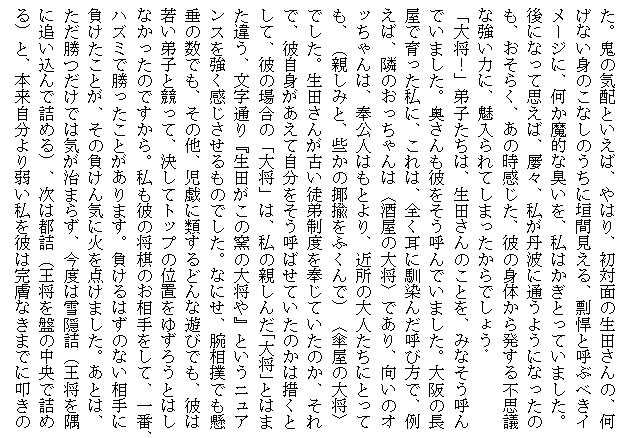
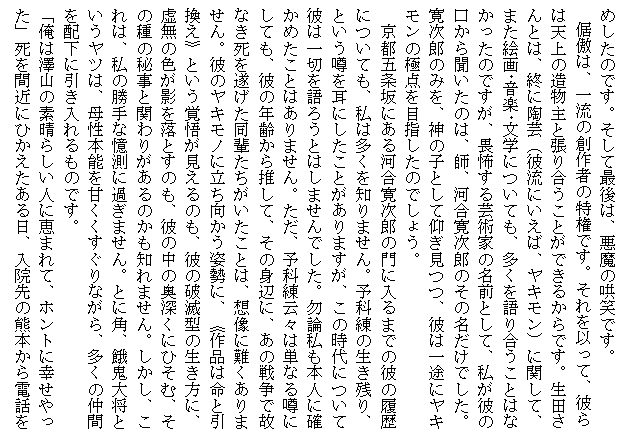
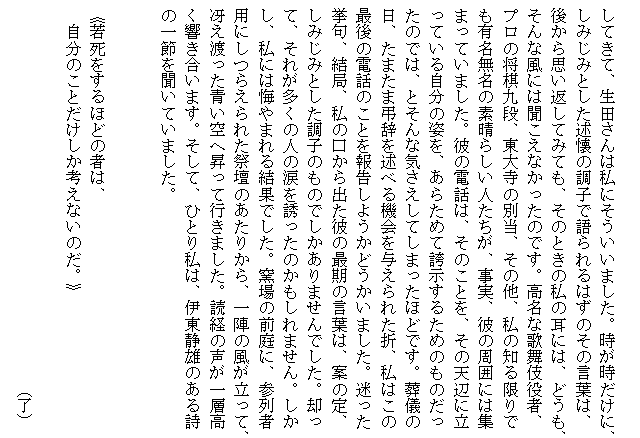
「日帰りで行けますか」
「大阪を朝八時の汽車でたてば、その日のうちには十分帰れますよ」
彼が独立し、丹波に窯を設けた時の支援者であるO氏に連れられて、はじめて、その窯場に
生田さんを訪ねたのは、もうずいぶん昔のことになりました。福知山線・相野駅からの乗合バ
スは、まだ人家の少なかった駅前の通りをすぐに抜けると、後は、山間の狭い凸凹道を、ひた
すら奥へ奥へと分け入っていきます。時折、長く伸び出た木々の小枝が、窓を叩く音がします。
生田さんを訪ねたのは、もうずいぶん昔のことになりました。福知山線・相野駅からの乗合バ
スは、まだ人家の少なかった駅前の通りをすぐに抜けると、後は、山間の狭い凸凹道を、ひた
すら奥へ奥へと分け入っていきます。時折、長く伸び出た木々の小枝が、窓を叩く音がします。
「奥さんは少々愛想はないが、悪い人間やないから、気にせんでよろしい。まあ、世間並みの
女なら、こんな寂しい山奥に嫁には来んやろうから……」
女なら、こんな寂しい山奥に嫁には来んやろうから……」
道中で聞いたO氏の話が、ふと思い起こされて、私は、まるで鬼の棲み家にでも誘い込まれ
るような気分になったものです。
るような気分になったものです。
褪せた藍色の筒袖の上衣に、同色の裁着袴を痩身に纏い、蓬髪に無精髭、出迎えてくれた
生田さんは、それなりに鬼に見えなくもなかったのですが、自然とかもし出される素朴な雰囲気
と、何といっても、人懐っこいその笑顔には、とりあえず私を安堵させるものがありました。その
日は、開店準備の、珈琲カップを注文するためにやって来たのですが、肝心の用件はそこそこ
に、結構、話が弾みました。奥さんは、鬼でも蛇でもなく、ごく普通の優しい女性でした。鬼の気
配といえば、やはり、初対面の生田さんの、何げない身のこなしのうちに垣間見える、剽悍と呼
ぶべきイメージに、何か魔的な臭いを、私はかぎとっていました。後になって思えば、屡々、私
が丹波に通うようになったのも、おそらく、あの時感じた、彼の身体から発する不思議な強い力
に、魅入られてしまったからでしょう。
生田さんは、それなりに鬼に見えなくもなかったのですが、自然とかもし出される素朴な雰囲気
と、何といっても、人懐っこいその笑顔には、とりあえず私を安堵させるものがありました。その
日は、開店準備の、珈琲カップを注文するためにやって来たのですが、肝心の用件はそこそこ
に、結構、話が弾みました。奥さんは、鬼でも蛇でもなく、ごく普通の優しい女性でした。鬼の気
配といえば、やはり、初対面の生田さんの、何げない身のこなしのうちに垣間見える、剽悍と呼
ぶべきイメージに、何か魔的な臭いを、私はかぎとっていました。後になって思えば、屡々、私
が丹波に通うようになったのも、おそらく、あの時感じた、彼の身体から発する不思議な強い力
に、魅入られてしまったからでしょう。
「大将!」弟子たちは、生田さんのことを、みなそう呼んでいました。奥さんも彼をそう呼んで
いました。大阪の長屋で育った私に、これは、全く耳に馴染んだ呼び方で、例えば、隣のおっち
ゃんは〈酒屋の大将〉であり、向いのオッちゃんは、奉公人はもとより、近所の大人たちにとっ
ても、(親しみと、いささ些かの揶揄をふくんで)〈傘屋の大将〉でした。生田さんが古い徒弟制
度を奉じていたのか、それで、彼自身があえて自分をそう呼ばせていたのかは措くとして、彼
の場合の「大将」は、私の親しんだ「大将」とはまた違う、文字通り『生田がこの窯の大将や』と
いうニュアンスを強く感じさせるものでした。なにせ、腕相撲でも懸垂の数でも、その他、児戯に
類するどんな遊びでも、彼は若い弟子と競って、決してトップの位置をゆずろうとはしなかった
のですから。私も彼の将棋のお相手をして、一番、ハズミで勝ったことがあります。負けるはず
のない相手に負けたことが、その負けん気に火を点けました。あとは、ただ勝つだけでは気が
治まらず、今度は雪隠づめ詰(王将を隅に追い込んで詰める)、次は都詰(王将を盤の中央で
詰める)と、本来自分より弱い私を彼は完膚なきまでに叩きのめしたのです。そして最後は、悪
魔の哄笑です。
いました。大阪の長屋で育った私に、これは、全く耳に馴染んだ呼び方で、例えば、隣のおっち
ゃんは〈酒屋の大将〉であり、向いのオッちゃんは、奉公人はもとより、近所の大人たちにとっ
ても、(親しみと、いささ些かの揶揄をふくんで)〈傘屋の大将〉でした。生田さんが古い徒弟制
度を奉じていたのか、それで、彼自身があえて自分をそう呼ばせていたのかは措くとして、彼
の場合の「大将」は、私の親しんだ「大将」とはまた違う、文字通り『生田がこの窯の大将や』と
いうニュアンスを強く感じさせるものでした。なにせ、腕相撲でも懸垂の数でも、その他、児戯に
類するどんな遊びでも、彼は若い弟子と競って、決してトップの位置をゆずろうとはしなかった
のですから。私も彼の将棋のお相手をして、一番、ハズミで勝ったことがあります。負けるはず
のない相手に負けたことが、その負けん気に火を点けました。あとは、ただ勝つだけでは気が
治まらず、今度は雪隠づめ詰(王将を隅に追い込んで詰める)、次は都詰(王将を盤の中央で
詰める)と、本来自分より弱い私を彼は完膚なきまでに叩きのめしたのです。そして最後は、悪
魔の哄笑です。
倨傲は、一流の創作者の特権です。それを以って、彼らは天上の造物主と張り合うことがで
きるからです。生田さんとは、終に陶芸(彼流にいえば、ヤキモン)に関して、また絵画・音楽・
文学についても、多くを語り合うことはなかったのですが、畏怖する芸術家の名前として、私が
彼の口から聞いたのは、師、河合寛次郎のその名だけでした。寛次郎のみを、神の子として
仰ぎ見つつ、彼は一途にヤキモンの極点を目指したのでしょう。
きるからです。生田さんとは、終に陶芸(彼流にいえば、ヤキモン)に関して、また絵画・音楽・
文学についても、多くを語り合うことはなかったのですが、畏怖する芸術家の名前として、私が
彼の口から聞いたのは、師、河合寛次郎のその名だけでした。寛次郎のみを、神の子として
仰ぎ見つつ、彼は一途にヤキモンの極点を目指したのでしょう。
京都五条坂にある河合寛次郎の門に入るまでの彼の履歴についても、私は多くを知りませ
ん。予科練の生き残り、という噂を耳にしたことがありますが、この時代について彼は一切を語
ろうとはしませんでした。勿論私も本人に確かめたことはありません。ただ、予科練云々は単な
る噂にしても、彼の年齢から推して、その身辺に、あの戦争で故なき死を遂げた同輩たちがい
たことは、想像に難くありません。彼のヤキモノに立ち向かう姿勢に、《作品は命と引換え》とい
う覚悟が見えるのも、彼の破滅型の生き方に、虚無の色が影を落とすのも、彼の中の奥深くに
ひそむ、その種の秘事と関わりがあるのかも知れません。しかし、これは、私の勝手な憶測に
過ぎません。とに角、餓鬼大将というヤツは、母性本能を甘くくすぐりながら、多くの仲間を配下
に引き入れるものです。
ん。予科練の生き残り、という噂を耳にしたことがありますが、この時代について彼は一切を語
ろうとはしませんでした。勿論私も本人に確かめたことはありません。ただ、予科練云々は単な
る噂にしても、彼の年齢から推して、その身辺に、あの戦争で故なき死を遂げた同輩たちがい
たことは、想像に難くありません。彼のヤキモノに立ち向かう姿勢に、《作品は命と引換え》とい
う覚悟が見えるのも、彼の破滅型の生き方に、虚無の色が影を落とすのも、彼の中の奥深くに
ひそむ、その種の秘事と関わりがあるのかも知れません。しかし、これは、私の勝手な憶測に
過ぎません。とに角、餓鬼大将というヤツは、母性本能を甘くくすぐりながら、多くの仲間を配下
に引き入れるものです。
「俺は澤山の素晴らしい人に恵まれて、ホントに幸せやった」死を間近にひかえたある日、入
院先の熊本から電話をしてきて、生田さんは私にそういいました。時が時だけに、しみじみとし
た述懐の調子で語られるはずのその言葉は、後から思い返してみても、そのときの私の耳に
は、どうも、そんな風には聞こえなかったのです。高名な歌舞伎役者、プロの将棋九段、東大
寺の別当、その他、私の知る限りでも有名無名の素晴らしい人たちが、事実、彼の周囲には
集まっていました。彼の電話は、そのことを、そのてっぺん天辺に立っている自分の姿を、あら
ためて誇示するためのものだったのでは、とそんな気さえしてしまったほどです。葬儀の日、た
またま弔辞を述べる機会を与えられた折、私はこの最後の電話のことを報告しようかどうか躊
躇いました。迷った挙句、結局、私の口から出た彼の最期の言葉は、案の定、しみじみとした
調子のものでしかありませんでした。却って、それが多くの人の涙を誘ったのかもしれません。
しかし、私には悔やまれる結果でした。窯場の前庭に、参列者用にしつらえられた祭壇のあた
りから、一陣の風が立って、冴え渡った青い空へ昇って行きました。読経の声が一層高く響き
合います。そして、ひとり私は、伊東静雄のある詩の一節を聞いていました。
院先の熊本から電話をしてきて、生田さんは私にそういいました。時が時だけに、しみじみとし
た述懐の調子で語られるはずのその言葉は、後から思い返してみても、そのときの私の耳に
は、どうも、そんな風には聞こえなかったのです。高名な歌舞伎役者、プロの将棋九段、東大
寺の別当、その他、私の知る限りでも有名無名の素晴らしい人たちが、事実、彼の周囲には
集まっていました。彼の電話は、そのことを、そのてっぺん天辺に立っている自分の姿を、あら
ためて誇示するためのものだったのでは、とそんな気さえしてしまったほどです。葬儀の日、た
またま弔辞を述べる機会を与えられた折、私はこの最後の電話のことを報告しようかどうか躊
躇いました。迷った挙句、結局、私の口から出た彼の最期の言葉は、案の定、しみじみとした
調子のものでしかありませんでした。却って、それが多くの人の涙を誘ったのかもしれません。
しかし、私には悔やまれる結果でした。窯場の前庭に、参列者用にしつらえられた祭壇のあた
りから、一陣の風が立って、冴え渡った青い空へ昇って行きました。読経の声が一層高く響き
合います。そして、ひとり私は、伊東静雄のある詩の一節を聞いていました。
《若死をするほどの者は、
自分のことだけしか考えないのだ。》
(了)
|
|

